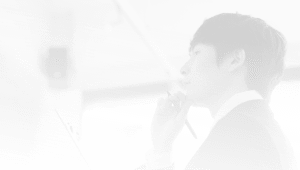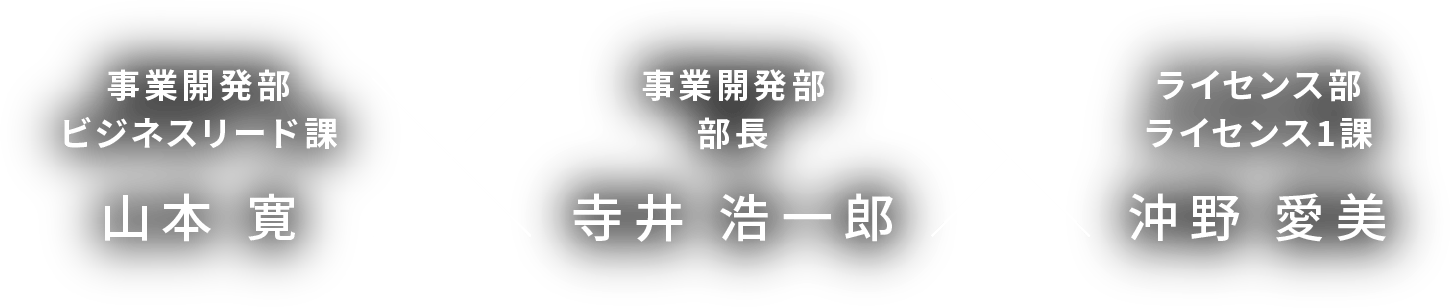
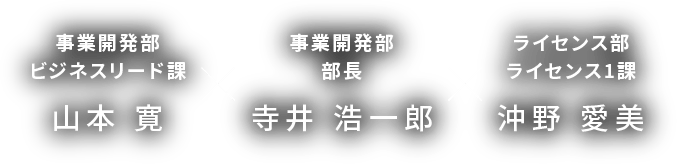
世界で挑む、
新薬候補の獲得
-核酸医薬という新たな領域-
SCROLL
2025年3月、小野薬品工業は、米国バイオ医薬品企業が
研究開発を進めてきた新薬候補に関して、
全世界を対象とした開発および商業化の権利を取得した。
小野薬品にとって核酸医薬という新たな領域、
かつ後期臨床開発品の全世界権利獲得という
初めての挑戦であり、
近い将来の
パイプラインの拡充という意味でも重要な一歩となる。
そして何より、患者さんにとって、
いまだ十分な治療の選択肢がない
疾患領域に革新をもたらす可能性をそなえている。
この大きな一歩が生まれた背景には、
企業や文化の違いを超え、
未知なる試練と
向き合い続けてきたメンバーたちの挑戦があった。
SECTION 01
患者さんの新たな“希望”となり得る、
新薬候補との出会い。
寺井 私たち事業開発部は、将来医薬品になり得る「新薬候補」の開発権や販売権について他社との提携を検討する役割を担っています。10年、15年先の未来をつくるのが創薬研究だとしたら、事業開発は5~10年先の未来をつくる仕事。近い将来、くすりとして世に出せる可能性をそなえた新薬候補を世界中から探し出し、会社にとって、そして何より患者さんにとって、良い選択肢になり得るのかを考えながら、新薬候補の価値を評価し、その開発企業と対話しています。

山本 私が事業開発部に異動してきたのは2022年のこと。米国で提携機会の探索をしているチームを通じてこの新薬候補の存在を知ったのも、同じ年のことでした。血液の病気の一つであり、赤血球が過剰に作られ、肺や心臓、脳などに血栓症ができやすくなる「真性多血症」に対する、くすりの候補です。現在、真性多血症の主な治療法として、定期的に血液を抜いて増え過ぎた赤血球を減らす「瀉血(しゃけつ)療法」、血栓症予防のための低用量アスピリン、赤血球をはじめその他血液細胞の産生を抑制する薬物療法があります。今回権利を取得した新薬候補は、患者さんにとって利便性が高く、治療の負担を軽減できる可能性を秘めています。世界中で病気と闘っている真性多血症の患者さんに希望を届けられるかもしれない。そして、小野薬品の成長にも貢献できるかもしれないと、強い魅力を感じました。
寺井 この新薬候補が世に出ることで、患者さんにとって新たな希望となり得るのではないかと私も考えています。その研究を手がけてきたのは、核酸医薬という領域において世界で最も特許出願件数の多いリーディングカンパニー。当然、私たち小野薬品だけでなく、多くの製薬企業が同社の創る新薬候補に注目しているはずです。ましてや時期としても、臨床試験の最終ステップを目前に控えた開発の後期段階にあり、大事な息子や娘のように育ててきた新薬候補を当社に託していただくことは、決して簡単なことではありませんでした。



SECTION 02
米国で粘り強く築き上げた、
人と人との関係。
山本 私たち事業開発部は、科学的な評価と、経済性の評価という大きく2つの観点から新薬候補を評価していくのですが、残念ながら一度目の評価時は臨床データも少なく、検討が中止になってしまいます。非常に残念に感じていましたが、再度この新薬候補の導入を検討する機会があるのであれば、ぜひとも担当したいと考え、米国の担当者と定期的なコミュニケーションを取っていました。
寺井 アメリカにいるメンバーたちも同じ気持ちで、再度交渉するチャンスを切り拓こうと諦めずに足繁く先方へ通い、コンタクトを取り続けてくれました。何度も顔と顔を合わせ、時には趣味や家族の話までして、お互いが大切にしていることへの理解を深め合い、人として、会社としての信頼関係を築いていったのです。

山本 正しく評価を行うためには、先方から必要な情報やデータを開示してもらわなければなりません。こうしたデータは製薬企業にとって生命線です。だからこそ、先方企業との交渉を通じて、小野薬品がなぜ、その情報を必要としているのか?書面だけのやり取りではなく、自分たちの想いや考えを真摯に伝えることが重要だと肌で学びました。

寺井 加えて、核酸医薬という領域自体が、小野薬品にとって前例のないチャレンジです。自分たちが分からないところや疑問点は、包み隠さず相手に伝え、お互いに時間をかけて、納得できるまで粘り強く話し合いを重ね、理解を深めていきました。こうした積み重ねや、なんとしても困っている患者さんに新薬を届けたいという強い思いがあったからこそ、契約締結に向けた交渉の道が拓けたのではないかと考えます。




SECTION 03
一丸となって取り組んだ先、
契約への道が拓けた。
沖野 契約交渉にあたってライセンス部として一つの山場を迎えたのは、ちょうど年末が差し迫る時期でした。通常であれば、契約書初案の社内レビューと対案の作成に1ヵ月はかかります。しかし、今回のプロジェクトでは先方企業の希望する契約締結時期を踏まえると、通常のタイムラインよりもスピード感のある対応が求められました。年始早々に先方企業が小野の対案をレビューし協議を加速できるよう、関係部署の方々にこの契約の重要性を丁寧に説明し、確認を急いでもらいました。この時、みなさん他のコア業務がある中で、「この導入には意義がある」と理解し、積極的に動いてくださったことで、一丸となって対案をまとめ上げることができ、最終的に契約締結に至りました。契約締結後、今回の新薬候補に小野薬品の“開発番号”が付いたという連絡をもらった時は、これからは自分たちが開発していくんだという実感がわき、嬉しく思いました。

寺井 ひとつの契約を締結させることは、並大抵のことではありません。私自身、アメリカ駐在時代、時間をかけて交渉を重ねてきた案件が最後の最後で他社に決まり、身を震わせるほど涙を流したことがあります。新薬候補のライセンス導入には必ず競合他社がいて、経済的な条件だけでなく、信頼関係の構築や対応のスピードなど、総力をあげた交渉が求められます。だからこそ、私たち事業開発部とライセンス部は日頃から綿密な連携をはかり、その先の開発や製造に関わる部門も含めて、多くの人たちの理解と協力を得られるように努めています。今回スピード感を持って契約を締結できたのは、まさに小野薬品のチーム力が発揮できたことが大きな要因だと考えています。





SECTION 04
自分たちの創意工夫で
薬の価値を高めることができる。
山本 これまで小野薬品が導入してきた新薬候補は、国内の権利に関するものがほとんどでした。しかし今回は、「全世界における権利を取得することで、世界中の患者さんに届ける道を拓く」という大規模なものになります。契約を締結して小野薬品が権利を取得した後は、自分たちでグローバルに開発を進めていくことになり、未知なるチャレンジの連続です。

寺井 そのため、今回のプロジェクトには、契約締結先の企業と小野薬品だけでなく、昨年(2024年6月)小野薬品グループに加わったばかりのDeciphera社との協力が欠かせませんでした。Deciphera社には、これからONOグループのグローバルにおける開発・販売を担う中心的存在になっていくことを期待しています。
山本 グループ化による統合が並行して進みつつあるものの、Deciphera社と小野薬品とでは、社風も、商慣習も、価値観も、仕事の進め方も異なります。こうした状況の中、Deciphera社のメンバーと、短い時間で目線を合わせ、契約締結に持ち込む必要がありました。はじめは、お互いに関係性を構築するところからのスタートでした。
寺井 我々が見ているものと、Deciphera社から見えているものに大きなギャップがあり、お互いの目線を合わせることが重要でした。例えば、臨床試験の設計の仕方によって、有効性、安全性における新たな価値を見出せたり、発売までの時間を短縮して患者さんにより早く届けたりすることもでき、薬の価値は大きく上がります。Deciphera社から欧州や米国の市場でその価値を高めることがいかに重要なのかという視点を学び、自分たちの創意工夫によって薬の価値をさらに高めていけるのだという気づきを得ました。こうした協議を重ねた結果、契約締結先の企業に対して、彼らが生み出した新薬候補をより良いかたちに育てていけるような提案ができたのではないかと考えます。

沖野 私たちライセンス部でも、他社との向き合い方を大切にしています。先方企業との契約交渉では、自社の利益を最大化できるよう自分たちの考え方や想いをきちんと主張し、相手の理解を得られるよう丁寧に説明します。一方でこちらの意見ばかりを主張するのではなく、相手の主張にも耳を傾け、お互いに歩み寄れる部分を探しながら、両社ともに納得しながら進んでいくことが大事だと感じています。




SECTION 05
私たちは5〜10年先の近い未来に、
どのような選択肢を提供できるか。
山本 自分が事業開発部に異動して初めて担当し、一度は断念した新薬候補の全世界における権利を得たことは、とても感慨深いものがあります。核酸医薬という領域は、私たちにとって未知なる領域ではありますが、製造の部門を含めて社内のメンバーは、この新たなチャレンジに対して積極的であり、これまで小野薬品がブレークスルーによって患者さんに新たな価値を届けてきたという企業文化を、改めて実感する機会にもなりました。

沖野 私は、自社の新薬候補を増やすというミッションに直接関われるこの仕事に、とてもやりがいを感じています。今回は一つ、契約まで結びつけられた。ですが、患者さんのためにも、小野薬品のためにも、さらなるパイプラインの拡充が待ち望まれています。これからも、次の新薬候補の導入につながるように、挑戦していきたいです。
寺井 新薬候補の導入には、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。将来的な売上予測を、精緻に組み立てることができるか。導出元となる企業にも株主がいるため、先方に対して適切な経済条件を提示できるか。科学的な根拠はあるか。そして何より、その先にいる患者さんにとって、より良い治療の選択肢になり得るかどうか?そんな中、私たち事業開発部では、「未来の常識を共創する」というスローガンを掲げています。私たちが見据えているのは5〜10年先。その近い未来に、どんな選択肢を提供できるのか。日々、社内外の多くの人と関わり、一人ひとりが感性と創造性を発揮しながら、これからもさまざまな可能性に挑み続けていきます。


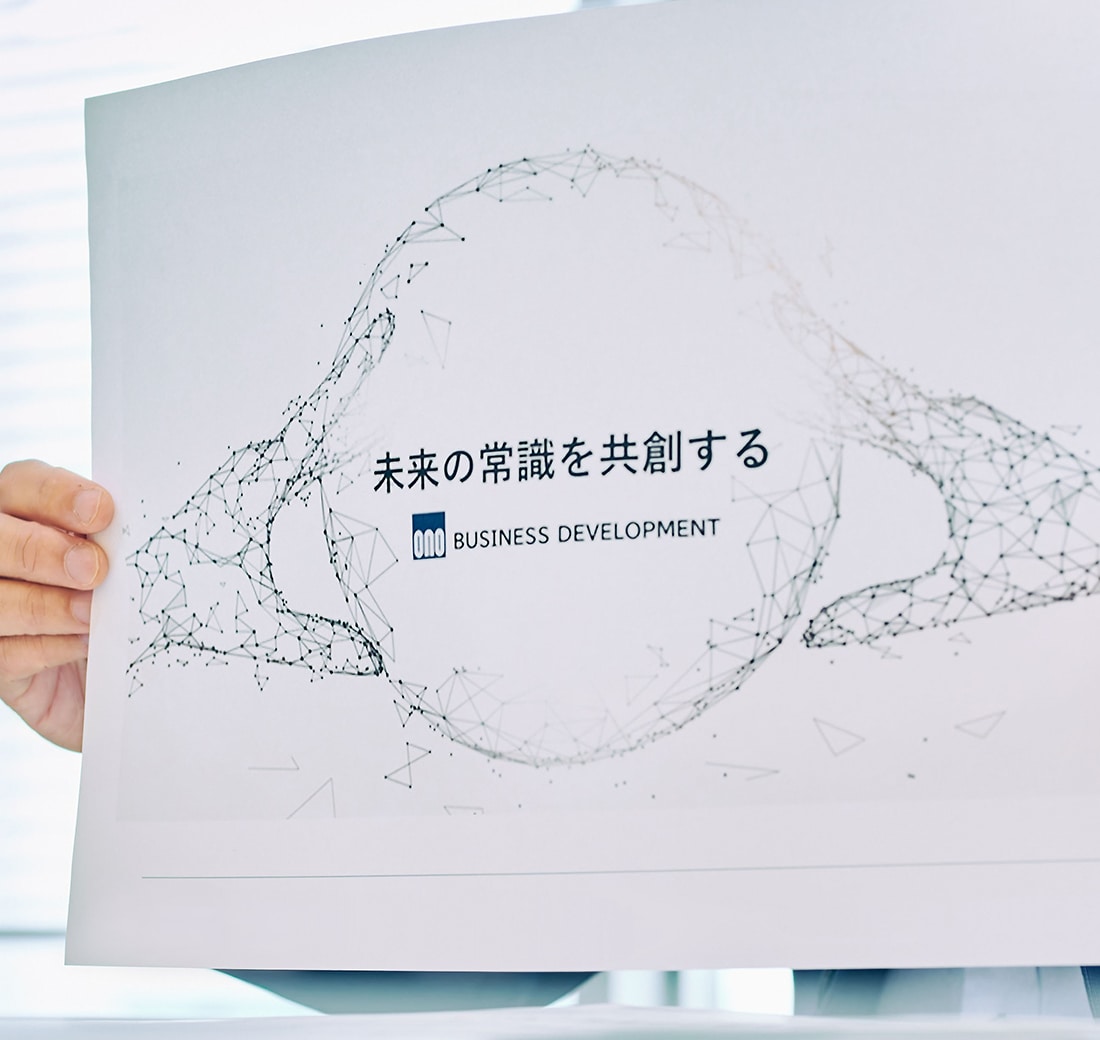
グローバル、核酸医薬品、
そして、文化の違いを超えて同じ思いを持つ仲間との共創。
私たちは、未知なるチャレンジを厭わない。
その先に、まだ見ぬ選択肢を待つ患者さんがいる限り。


事業開発部 ビジネスリード課
山本 寛
小野薬品の創薬の手法に惹かれ、2009年に入社。創薬研究や研究提携業務に携わった後、事業開発部に異動し、新薬候補を中心とした提携活動に従事。現在は、ビジネスリード課にて中期経営計画の達成に向けた事業開発部の活動の戦略・戦術の立案に取り組む。


事業開発部 部長
寺井 浩一郎
1995年、小野薬品工業に入社。免疫・アレルギー領域の研究に携わった後、営業本部にて販売活動の支援、開発本部で米国・日本を対象とした自社創製品の開発計画の立案や、国際部でのパイプライン拡充を担い、約4年半にわたるアメリカ駐在を経験。現在は、事業開発部のリーダーとして新薬候補の導入をめざしたライセンス活動を推進する。


ライセンス部 ライセンス1課
沖野 愛美
2017年入社。神戸・大阪エリアでMRとして、医療現場に治療薬の情報を届ける活動に従事。その後、社内公募制度にチャレンジしてライセンス部へ異動。契約書のレビューや交渉、売上予測や事業採算性の検討など、ライセンス締結に関わる幅広い業務に取り組む。
2025年5月現在